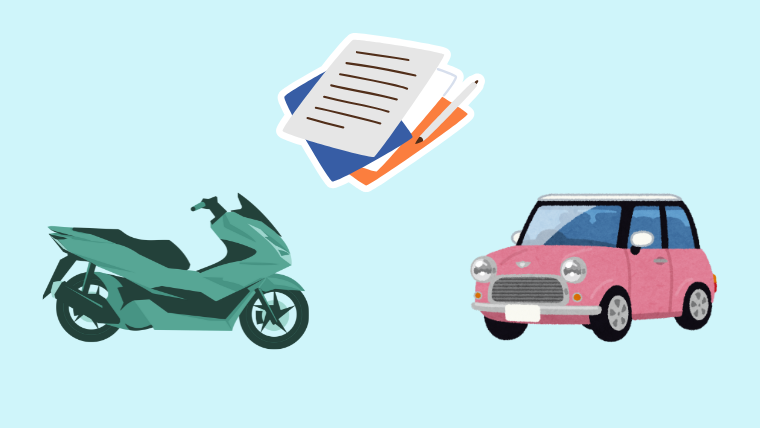最近行った手続きをお話いたします。
今は乗らないバイクであるが、まだ手元に置いていたい。
でも、税金を払いたくない。
このような場合の手続きについて、どこで、何をすれば良いかをお伝えします。
3月末までに手続きを済ませると、翌年4月の自動車の税金を課されなくなります。
ただ、3月は年度末であり、自動車関連の窓口が大変混雑します。
できる方は早めのお手続きを検討されると良いでしょう。
バイクのタイプを確認
登録を消すための手続きが必要です。
バイクのタイプを確認します。
二輪であって、排気量が何CCであるかによって窓口が異なります。
| 種類 | 排気量 | 窓口 |
|---|---|---|
| 小型二輪 | 250ccを超える | 運輸支局等 |
| 軽二輪 | 125㏄を超え250cc以下 | 運輸支局等 |
| 原動機付自転車 | 125cc以下 | 市区町村役場 |
運輸支局等とは、登録してある地域を管轄する各運輸支局や自動車検査登録事務所です。
神奈川県と東京都の運輸支局等を別記事でご紹介しています。
神奈川→→神奈川の運輸支局等がわかるページはこちらから
東京→→→東京都内の運輸支局等がわかるページはこちらから
本記事では、以下、小型二輪(自動二輪)についてお伝えします。
四輪の登録自動車、軽自動車、軽二輪、原付バイクは、別の手続きになりますので、ご了承くださいませ。
文章の一部は四輪自動車との手続きの比較も書かせていただいておりますが、基本は小型二輪のお話になります。
税金を止めるためには
登録を抹消する車について、次年度の税金支払いを止めるためには、以下の手続きが必要です。
いわゆる廃車の手続きと
税金を止めるための手続き
いずれも、同じ窓口で申請を済ませることができます。
いわゆる廃車の手続きは書類が数通必要ですし、ナンバープレートも必要です。
税金を止めるための手続きは、一通の書類が必要です。
順にお伝えします。
廃車?
廃車というと、以下のようなイメージがありました。
~「廃車」のイメージ~
・壊して役目を終了させたバイクについて届け出る手続き
・「その」バイクの車体はどんな手段をもってしても今後二度と乗れない届出の手続き
けれども、正確には、少し広い意味があるようです。
登録しない
公道で使用しないための手続き
が、いわゆる廃車の手続きだと考えて良いと思います。
今回私が手続きを行ったバイクは、姿が「バイクそのもの」です。
めちゃめちゃに壊して廃棄寸前・・というわけではありません。
輸出するわけでもありません。
バイクそのものは存在したまま、登録を外す、登録を抹消する手続きなのです。
この登録抹消手続きもいわゆる「廃車」手続きに含まれているようです。
行政の手続きの用語として「廃車」という言葉は使われていませんが、案内の冊子にカッコ書きで「廃車」という言葉を使っている箇所があります。
廃車は、「登録」の反対語の意味だと考えればスムーズかと思います。
税金の関係については、
登録しない=公道を走らない=税金はかからない
と言えます。
新車でまだ登録しない自動車も私有地内で存在しています。
古くて登録をしない自動車も私有地に置いてあっても構いません。
存在していることには変わりありません。「登録しているか、していないか」が違うだけです。
手続きの名称
小型二輪の「廃車手続き」は、「自動車検査証返納」という手続きになります。
この「自動車検査証返納」は、車検証の返納なのですが、申請すると、登録が抹消されます。
登録抹消となると、「自動車検査証返納証明書」が交付されます。
四輪自動車の場合は、「一時抹消」という手続きになります。
四輪自動車で、もう二度と誰も乗らないという手続きは「永久抹消」という手続きになります。
自動車検査証返納の手続き ~概要~
小型二輪の登録抹消は、「自動車検査証返納」の手続きとなります。
必要な物は次のとおりでした。
・車検証(原本)
・自動車検査証返納証明書交付申請書(車検証を返納するための申請書)
・所有者の認印
・軽自動車税申告書(税金を止めるための申請書)
・手数料納付書
・ナンバープレート
申請代理人が行く場合 ~代理のための特別な持ち物は不要~
申請代理人が窓口に行きましたが、委任状は不要でした。
したがって、実印のある委任状・印鑑証明書も不要です。
申請代理人は、申請書に名前と電話番号を書くだけで申請代理人の本人確認はありませんでした。
次に書く四輪よりも簡単な手続きになっています。
四輪の場合と比較
四輪の「一時抹消」の方が小型二輪より慎重な手続きになります。
四輪の場合は、申請代理人が窓口に行くとき、委任状(実印で押印)と印鑑証明書が必要になります。
小型二輪の車検証返納手続き ~必要な物を詳しく~
小型二輪の自動車検査証返納手続きについて、必要な物を詳しくお伝えします。
必要な物1,車検証
車検証は必ず原本を持って行きます。
期限切れであっても、その車検証を持参します。
必要な物2,自動車検査証返納証明書交付申請書
こちらは、車検証を返納し、その証明書をもらうための書類です。
運輸支局や、自動車登録検査事務所に備え付けてあります。
「第3号様式の2」というものを使用します。
必要な物3,認印
「必要な物2」の申請書には、所有者の押印欄がありまので、そこに認印を押します。
実印は不要です。
所有者本人が窓口に行く際は、認印を持参し、その場で申請書を作成・押印し、提出します。
申請代理人が窓口に行く際は、予め作成した申請書に所有者が押印し、その申請書を持参する流れとなります。
必要な物4,軽自動車税申告書(税金を止めるための申請書)
小型二輪の税金は、県ではなく市町村に納めます。(神奈川なので「県」と書いています)
毎年4月1日に登録されている車に税金が課されるところ、前年度に「登録しないバイク」となりますので、税金支払いをしなくてよくなります。
税金を止めるには、市町村への手続きが必要です。
次年度の課税を停止するための申請書として、「軽自動車税申告書」を作成します。
この書類を受理してもらうことで、翌年度の税金の支払いを停止することができます。
税止めの書類と言っています。
四輪の自動車の場合には、県税の書類になるため、神奈川県の「「自動車税申告書」が必要になります。
必要な物5,手数料納付書
手数料は350円でした。
印紙を購入して貼り付けました。
必要な物6,ナンバープレート
二輪車のナンバープレートは簡単に外すことができます。
プラスドライバーを用意し、「時計と反対方向」に回すと外すことができました。
運輸支局での動き
まずナンバープレートを返納しました。
手数料を納付し、返納の窓口で、手数料納付書に押印してもらいます。
次に、申請書一式を登録部門の窓口で提出しました。
最後に、交付の窓口で、自動車検査証返納証明書を受け取って終了です。
運輸支局は様々な窓口があり、どこに行くのか迷うと思います。
相談窓口でさえ、どこが適切なのかわかりづらいという印象でがあります。
混雑の状況にもよりますが、時間がかかると想定して出かけた方が良いと思います。
お忙しい方に、代行サービスのご案内
運輸支局や自動車登録検査事務所での手続きは、慣れていないと、複雑で面倒です。
神奈川県内でお手続きが必要でしたら、当サイトの事務所に代行させてみませんか?
行政書士やまおか事務所では、ご依頼に応じて自動車の登録抹消申請等を代行いたします。
当事務所の行政書士、山岡でございます。

当事務所の特長は「お客様を不安にさせない適切な連絡」です。
ご依頼の結果を出すのは当たり前。
同じ結果を出す中で「当事務所は何ができるか?」を考え、お客様に安心していただけるサービスを大切に考えています。
やり取りしなければわからない部分であり、他の事務所と比較しなければ理解しにくいかもしれませんが、私どもは誠実に対応させていただきます。
当事務所への連絡は、お電話または送信用フォームをご利用くださいませ。
行政書士やまおか事務所
電話 070-7519-8731
または 045-514-7400
営業時間は平日の10時から17時までです。